目次
疑義解釈資料(平成30年)
問 80 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上ある場合とは、具体的にはどのような場合が含まれるのか。
(答)過去1年以内に、心不全による当該患者の病状の急変等による入院(予定入院を除く。)の期間が2回以上ある場合を指し、必ずしも2回以上の入院初日がある必要はない。
なお、当該保険医療機関以外の医療機関における入院であっても当該回数に計上して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 81 「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない」とあるが、具体的にはどのような取扱いか。
(答)緩和ケアチームの構成員がいずれも専任であるとして届出を行った場合、1日に当該加算を算定できる患者数は 15 人までとなる。
1日に当該加算を算定する患者数が 15 人を超える場合については、緩和ケアチームの構成員のいずれか1人が専従であるとして変更の届出を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 82 緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料の施設基準における「精神症状の緩和を担当する医師」は、心療内科医であってもよいか。
(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問53)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。
(答)対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問54)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定
- ISO(国際標準化機構)9001の認証
(答)①及び②ともに該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問1)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定
- 公益財団法人日本医療機能評価機構の緩和ケア推進支援の認定
- ISO(国際標準化機構)9001の認証
疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問52) 緩和ケア診療加算の要件である「緩和ケア病棟等における研修」には、どのようなものがあるのか。
(答) 現時点では、従来からの以下の研修
- 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」又は「乳ガン看護」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程に加え、日本看護協会認定看護師教育課程「がん放射線療法看護」のいずれかの研修と考えている。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問53) 「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等」とは他に何があるのか。
(答) 例えば、日本緩和医療学会が主催した緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問54) がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会を修了したことを確認できる文書とは厚生労働省健康局長印のある修了証と考えてよいか。
(答) よい。ただし、発行に時間がかかる等の場合はその他の証明できる文書を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問55) 緩和ケア診療加算等の要件にある「がん診療連携拠点病院に準じる病院」とは何か。
(答) 当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと都道府県が認め、医療計画、都道府県がん対策推進計画等で定めた病院が想定される。

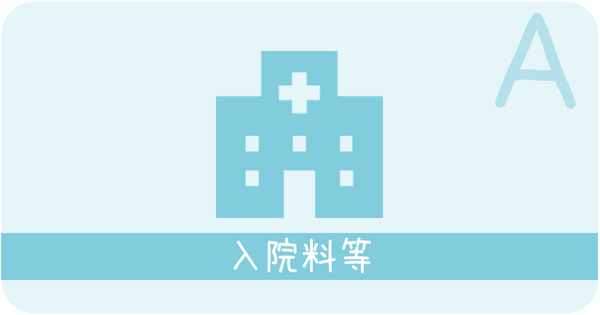



… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
… [Trackback]
[…] There you will find 4684 more Information to that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 40330 more Info to that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
tender piano jazz
tender piano jazz
… [Trackback]
[…] Find More on on that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
relax music
relax music
bossa nova
bossa nova
gangster rap music
gangster rap music
jazz music meaning
jazz music meaning
relaxing hymns
relaxing hymns
smooth piano jazz
smooth piano jazz
best mafia music
best mafia music
gym music 2023
gym music 2023
calm music
calm music
relaxing sleep music
relaxing sleep music
smooth jazz
smooth jazz
water music
water music
Saxophone
Saxophone
Relaxing Jazz
Relaxing Jazz
healing music
healing music
relaxing music
relaxing music
jazz instrumental
jazz instrumental
smooth night jazz
smooth night jazz
meditation music
meditation music
calm jazz
calm jazz
coffee shop jazz
coffee shop jazz
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
melhores músicas de hip hop para treinar
melhores músicas de hip hop para treinar
winter jazz relaxing
winter jazz relaxing
soothing piano
soothing piano
piano music
piano music
spa music
spa music
winter cozy jazz
winter cozy jazz
relax
relax
jazz music
jazz music
deep sleep
deep sleep
sleep meditation
sleep meditation
gym workout
gym workout
bass japanese type beat 2024
bass japanese type beat 2024
jazz cafe
jazz cafe
relax everyday
relax everyday
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: ika-qa.com/qa_a226-2/ […]
coffee shop ambience
coffee shop ambience
bossa nova cafe jazz
bossa nova cafe jazz
relaxing piano music
relaxing piano music
warm jazz music
warm jazz music
smooth bossa nova jazz
smooth bossa nova jazz
jazz bossa
jazz bossa
jazz relaxing music
jazz relaxing music
relaxing bossa nova
relaxing bossa nova