目次
疑義解釈資料(令和4年)
問 131 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)現時点では、日本病態栄養学会及び日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 132 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間及び指導回数の基準はないのか。
(答)一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間及び指導回数を個別に設定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 133 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、注3に規定する専門的な知識を有する管理栄養士が、同一月に初回の指導を 30分以上、2回目の指導を 20 分以上実施した場合は、どのように考えればよいか。
(答)注3の所定点数を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 134 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する場合、対面で実施する必要があるのか。
(答)情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。
なお、留意事項通知の(12)と同様の対応を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 135 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、入院中の患者が退院した後、初回外来時に外来栄養食事指導を実施する場合、情報通信機器等を用いて実施することは可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 136 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、「初回から情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること」とされているが、患者の入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合であっても、当該患者が退院した後に改めて指導計画を作成する必要があるか。
(答)不要。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 137 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。
(答)原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(令和2年)
問 67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
(答)メールのみを使用した指導では算定できない。
なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問184)同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)算定できない。同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。
なお、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問185)入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。
(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問17)平成28年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問184の答において「当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。」とあるが、外来患者が自ら診療を中止した後に数か月以上にわたり受診せず、新たに別の疾病で診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合も、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)このような事例についても、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けていた場合はその全ての診療)が終了したと医師が判断し、医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問31) 食事計画案等を必要に応じて交付すればよいこととされているが、計画等を全く交付せずに同指導料を算定することはできるのか。
(答) 初回の食事指導や食事計画を変更する場合等においては、患者の食事指導に係る理解のために食事計画等を必ず交付する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問27)小児食物アレルギー食を必要とするものに対する栄養食事指導料の算定は、小児食物アレルギー検査を実施済みの患者に対して行った場合に限定されるか。
算定の対象者の年齢制限はあるか。
また、他の医療機関で検査を受けた者に対して指導を行った場合でも、算定可能か。
(答)食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児が対象。検査結果の提供を受けていれば、他の医療機関で検査を受けたものでもよい。

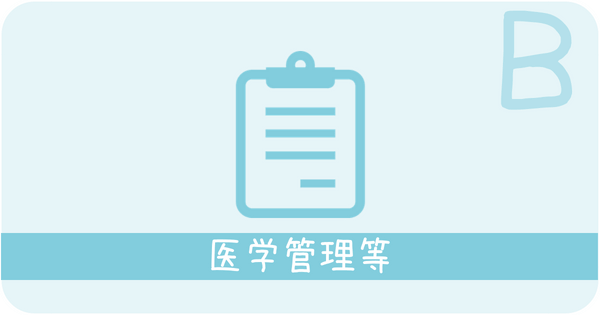




… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] There you can find 19678 additional Info to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Info here on that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 85231 more Info to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: ika-qa.com/qa_b001_9/ […]